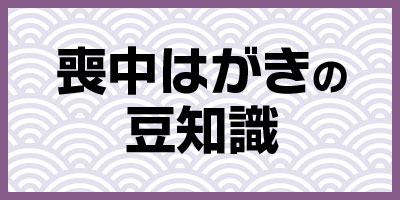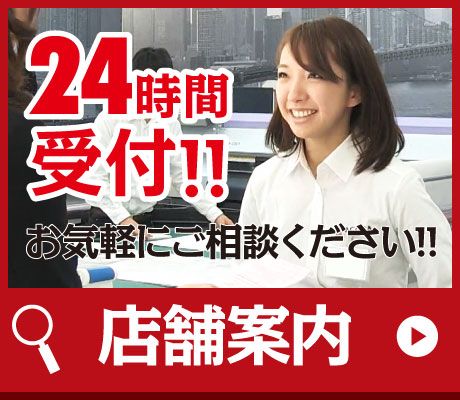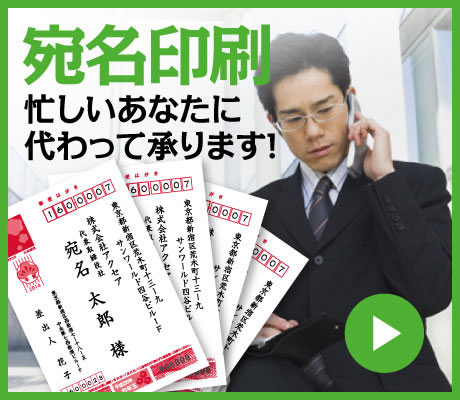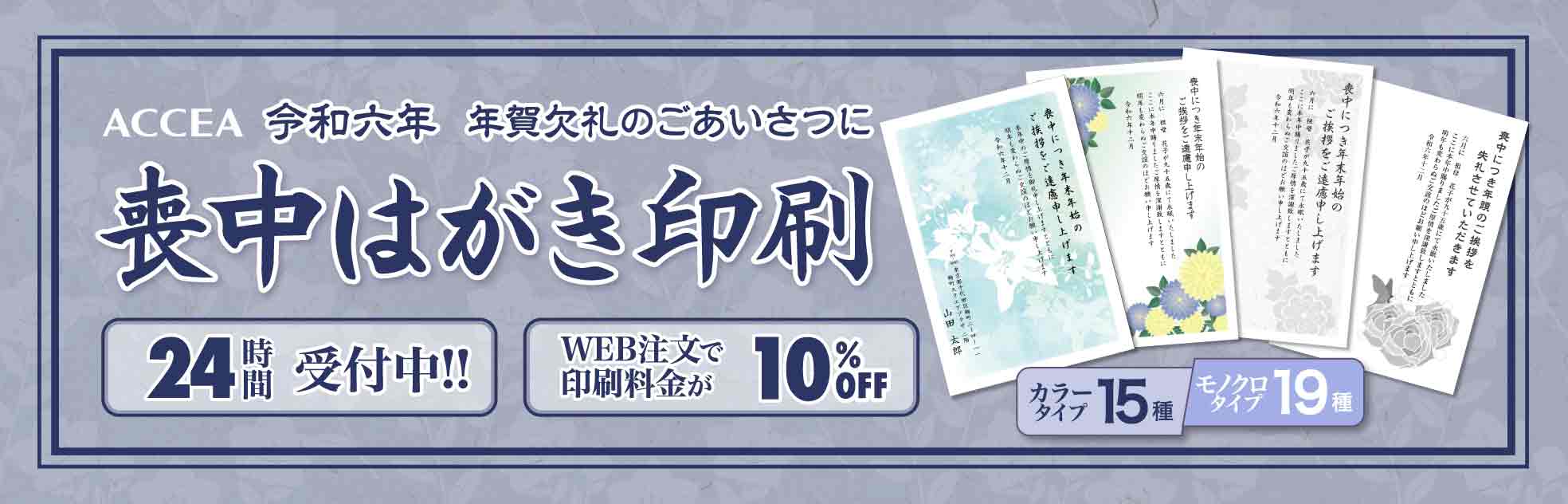喪中はがきの豆知識
喪中はがき、いざ出すとなると意外と知らないことが多いですよね。
「誰にだせばいいの?」「内容は?」「喪中の範囲って?」
送る方に失礼のないよう基本的なマナーはしっかりと学んでおきましょう。
【喪中とは?】
そもそも世間一般で言われる「喪中」とはどういう意味でしょう。
「喪中」とは「近親者が亡くなった時、一定期間その死を悲しみ世俗との交わりを避けて暮らすこと」です。
亡くなった人をおもい、静かに暮らす大切な期間です。
決まった期間はありませんが、一般的には忌明け(四十九日)を過ぎて半年から一年間程とされています。


喪中の歴史
喪中について、現代では特に定められた法律やルールはありません。
しかし、昔は法律にて期間や禁止事項などが定められていました。
喪中について書かれている法令は
奈良時代の「養老律令(ようろうりつりょう)」、江戸時代の「服忌令(ぶっきりょう)」です。
この江戸時代に定められた「服忌令(ぶっきりょう)」を明治時代に武家式と公家式に見直し、
「太政官布告」として全国に一斉に公布されました。
この中で定められている「服喪期間」“父母の13か月”が、
現在の「喪中期間は約1年」の起源になっているといわれています。
喪中に控えるべきこと
基本的には「静かに生活する期間」となりますので、
おめでたい事(お祝い事)は控えたほうがいいとされています。
例として
・お正月行事(門松・鏡餅を飾る、初詣に行く、年賀状を送らない)
・結婚式
・旅行
などがあげられます。
こちらも決まった法律はありませんが、
各家庭や地域の習慣によっても違いがありますのでそちらも確認してみましょう。
喪中となる範囲
どこまでが喪中の範囲となるのか、ふと疑問に思うこともありますよね。
基本的には、「2親等内の親族」がなくなった時に喪中とすることが多いようです。
| 0親等 | 夫・妻 |
| 1親等 | 父母・配偶者の父母・子供 |
| 2親等 | (自分の)兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者、祖父母、孫 (配偶者の)兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者、祖父母 |
【喪中はがきとは?】
自身が「喪中」となった場合、
年末が近づくにつれ気になるのが「喪中はがきはどうしたらいいのか」ということではないでしょうか。
喪中はがきとは、「年賀欠礼の挨拶状」といい、
「今年、年賀状はだしませんよ。だせませんよ。」ということを伝えるための挨拶状です。
決して喪中であることや、年賀状が不要であることを皆に伝えるものではありません。
内容や送る時期などに注意が必要です。

送る時期
相手が年賀状の準備をされる前にお送りすることが望ましく、
11月下旬から12月上旬に先方に届くように送るのが一般的です。
あまり早く出しすぎると相手が気遣いを長く続けることになりますの注意しましょう。
年末に亡くなった場合などは寒中見舞いはがきを使って欠礼をお詫びします。
送る相手
ご自身の知り合い全員に送る、というよりも「年賀欠礼の挨拶状」であることを考えると、
普段年賀状のやり取りをしている方に送るのが良いでしょう。
1-2年前までに年賀状をいただいていた方をリストアップし送るといいですね。
(1年前の方だけですと、その方が喪中期間でお送りできなかった可能性もあります。)
また、親族には「2親等」までは知らせる方が良いでしょう。
書く内容
内容としては大きく5つの項目に分かれ、句読点は使いません。
また本文中には、故人の逝去・年賀欠礼以外のことは書かないのが基本です。

- ①自分が家族・親族の喪に服していることをを伝える。
(時候の挨拶は不要)
- 「例:喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます」
- ②亡くなった方との続柄、亡くなった方のお名前、年齢、亡くなった日を伝える。
(誰がなくなったから、自分が喪に服しているかを説明)
- 「例:〇月に 祖母 ○○が○○歳にて永眠いたしました」
- ③結びの挨拶
(日頃のお付き合いへの感謝、先方の無事を祈る言葉)
- 「例:ここに本年中賜りましたご厚情を深謝いたしますとともに明年もかわらぬご交誼のほどお願い申し上げます」
- ④差出月
(差出月は先方(受け手)に届く月にしましょう。)
- 「例:令和元年12月」
- ⑤差出人